 埼玉県立近代美術館で開催中の「日本におけるキュビスム ― ピカソ・インパクト」に訪れた。わたしはわりに近くに住んでいるのだが、この美術館を訪れたのは、草間彌生展以来二度目である。あのときは大盛況だった模様で、たしかに展示も充実していて面白かった。エントランスにも草間彌生印の水玉模様が施されていて、吹き抜けになっている場所に巨大な人形があったのがよく記憶に残っている。かなり昔だったように思っていたのだが、いま調べると2012年の春ことだったようだ。
埼玉県立近代美術館で開催中の「日本におけるキュビスム ― ピカソ・インパクト」に訪れた。わたしはわりに近くに住んでいるのだが、この美術館を訪れたのは、草間彌生展以来二度目である。あのときは大盛況だった模様で、たしかに展示も充実していて面白かった。エントランスにも草間彌生印の水玉模様が施されていて、吹き抜けになっている場所に巨大な人形があったのがよく記憶に残っている。かなり昔だったように思っていたのだが、いま調べると2012年の春ことだったようだ。
平日の昼間だったので、案の定、ひとの入りは疎らだった。おそらく、同時にいたのは全体で10人程度にすぎないのではないかと思う。あまりにも混雑しすぎている状況に比べればよほど好ましいのだが、かといってこれだけ少ないといくらか淋しい気もしてしまう。首都圏とはいえ埼玉県という僻地にある立地の問題なのか、あるいは企画展の訴求力の問題なのか(とはいえ「ピカソ・インパクト」は、それなりにポップであるはずなのだ)わからないのだが、中小の美術館の運営は、ここにかぎらずどこも深刻な問題があることはおそらく間違いないだろう。
さておき、「日本におけるキュビスム ― ピカソ・インパクト」。わたしは、実際に展示を観るまでこのタイトルに半ば騙されていたのだが、前者と後者は、ある種のふたつの独立したテーマであって、その接合が試みられている展示だった、ということがわかった。
つまり、日本においてキュビスムがはじめに受容された1910年代後半から20年代にかけた大正期が前者に対応しており(もちろん、キュビスムの創始者でもあるピカソの影響下において受容がなされている)、第一部「日本におけるキュビスム」では、当時の日本人画家によるキュビスムの模倣作品が展示されている。
一方で、第二部「ピカソ・インパクト」では、1951年に東京と大阪で大規模なピカソの展覧会が開催されたされたことをきっかけとして、さまざまなジャンルにおいて横断的にピカソの影響が見られる作品群をおもに扱っている。すなわち、それらはかならずしも「キュビスム」とは分類されない。たとえキュビスト的手法をもちいていたとしても、それらはあくまで方法論における受容であるということだ。
「この展覧会はキュビスムが二度にわたって、別々の文脈で日本の作家たちに受容されたという仮説に基づいて組み立てられています」と紹介文にもはっきりと言明されているように、その隔たった二つの時代における受容のされかたの違いというコントラストが展示にもはっきりと示されており、その点では非常に優れたキュレーションの展覧会だったように思われる。
一部において印象的だったのは、日本における初期のキュビスムの受容で特筆すべきが、日本の作家たち(多くは1910年代のパリを知る者たちである)によるキュビスムへの理解/定義が非常に曖昧であったということである。日本におけるキュビスムは、西欧とは異なり、さほど他のイズムと区別されることのないままに作品がつくられていった。もちろん、このことは非常に興味深い点である。
たとえば、さまざまな批判は寄せられてきたものの、西欧における通俗的理解では、キュビスムはシュールレアリスムの対極としてあった。というのも、前者は画面をファセットによって分断し再構築するという論理的な思考に裏付けされた合理主義であり、後者は夢や無意識の表現に主軸をおいた非合理主義だからである。このような合理主義/非合理主義の二項対立は、キュビスムの影響下にある大正期の作品にはさほど認めることができない。キュビスムは、フォービズムと混濁され、シュールレアリスムやダダイスムとも区別されないまま、日本で模倣されていったのである(とはいえ、萬鐵五郎の作品からは、かれがキュビスムの論理的構造を深く理解していたことが伺える、とキャプションには記されていた)。
しかし、この風潮は長く続くことはなかった。作家たちはキュビスムの作品をつくることをすぐに辞めてしまう。多くの者たちがまたべつの作風に手を出し、それぞれの道は分岐していくというのだ。このことは、たとえばピカソやブラックが同じような作品を制作し続けなかったことにも関係しているのだろう。したがって、日本ではシュールレアリスムの作品は厚みがあっても、キュビスムの作例はあまり多く残されていないそうである。
それでも、キュビスムが途絶えたとするのは早計である、と主張するのが第二部の「ピカソ・インパクト」であった。わたしは第二部が非常に充実していたように思う。というのも、さきほど書いたように、第二部はキュビスムの枠組みから大きくはみ出て、同時期に制作されたさまざまな作品が並べられているのだが、一見するとそれらのうちに共通点を見出すほどが難しいほどかけ離れた作風の作品もある。しかし、「ピカソ・インパクト」「キュビスム」という概念によって、不思議と文脈が浮き上がってくるようなのだ。このことは、キュレーターの力量が存分に発揮されているところだろう。前ぶりもなく河原温《肉屋の内儀》が展示されていたのには驚いたが、「そう言われてみればそうかもしれない…」と作品と睨めっこをし、周囲の作品を見渡すという経験はなかなか愉快であった。
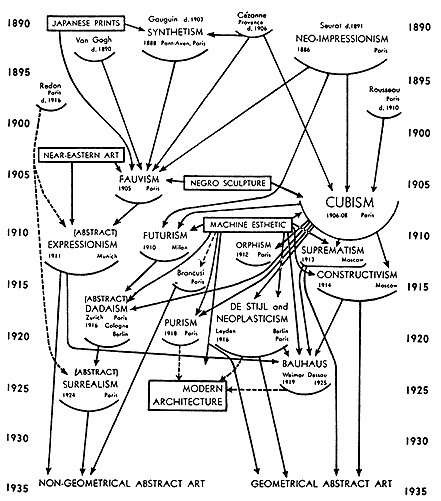
インターネットで調べていると、以上のような近代美術チャートが見つかった。「キュビスムと抽象芸術」展カタログに掲載された、アルフレッド・バー・Jrによる系統図だそうだが、この展示に際して講演を行った尾崎信一郎氏が紹介したそうである。わたしはこのあたりについての全体の見取り図は持ち合わせていなかったので、とても参考になる。そして、さまざまな20世紀のイズムの源流に位置する作家として、ヴァン・ゴッホとセザンヌはもちろんのことながら、ルドンとルソーの名が挙がっていることに成る程な、と思った。このへんはもう少し勉強したい限りである。
さて、「日本におけるキュビスム ― ピカソ・インパクト」で好きだった作品を列記して筆を措く。もう見れる機会はそうそうなさそうな作品ばかりであった。東郷青児《コントラバスを弾く》、普門暁《鹿・青春・光・交叉》、黒田重太郎《マドレエヌ・ルパンチ》、鶴岡政男《人(14)》《夜の群像》、下村良之介《祭》、池田龍雄《十字街》、尾藤豊《変電所》など。

とくに下村良之介《祭》は、すごく大きな作品で、カンバスの隅々までにエネルギーが充填しているうえに、表題からもわかるように、きわめて日本的なモチーフを配置しているお気に入りの作品だった。このモダンな造形、モチーフの配置の方法に、確かにピカソの影響が伺えるような気もする。
東郷青児も非常に良かったのだけど、初期には彼がキュビスムの作品を制作していたとはまったく知らなかった。そして、どうやら2017年の秋には損保ジャパン日本興亜美術館で生誕120年 東郷青児展が開かれるそうだ。こちらにも忘れないように足を運ばなければ。
さきほどの尾崎信一郎氏によるレクチャーの実況まとめ。こういう実況は本当にありがたい。このような知は積極的に共有されていくべきであろう。